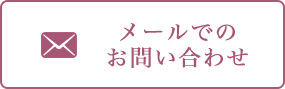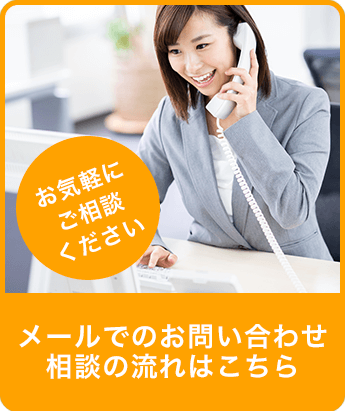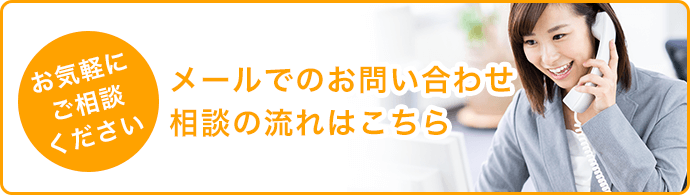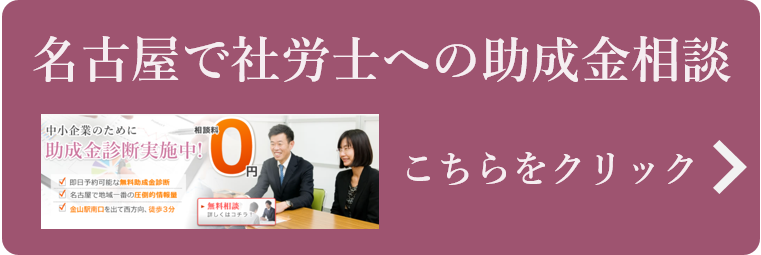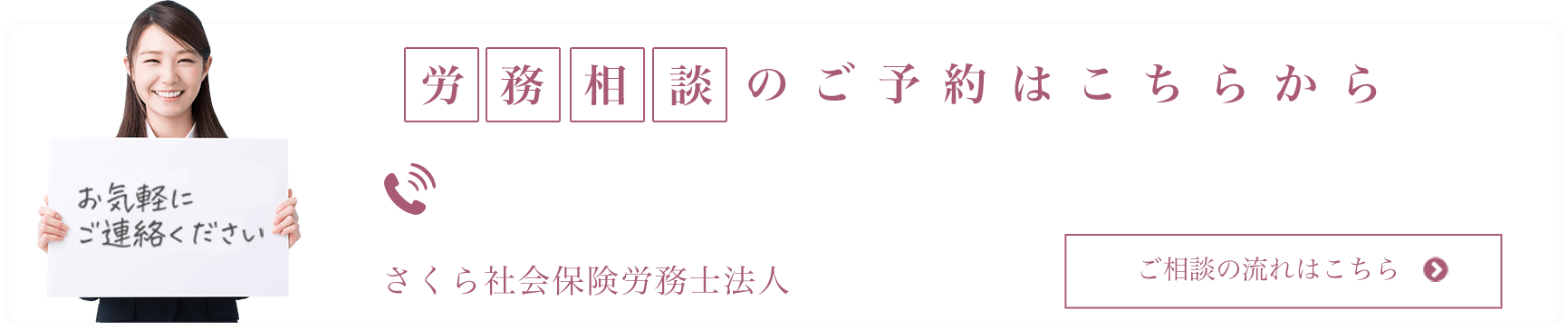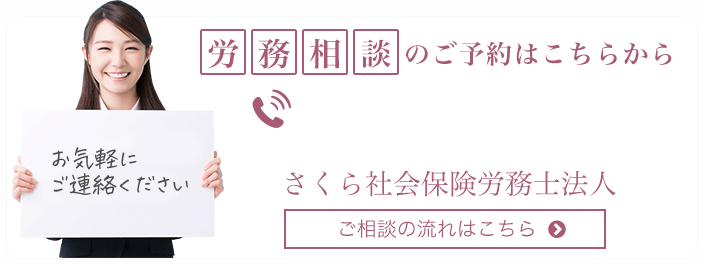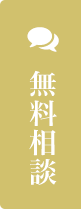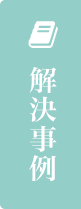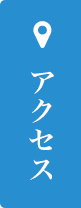パート・アルバイトの年次有給休暇について
- 2024.01.24 コラム
 さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。
さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。
はじめに
働き方改革の流れの中で、残業など労働時間以外に年次有給休暇についても注目されるようになりましたが、パート・アルバイトに対する有休はまだ整備されていない事業所も少なくありません。
近年、労働基準監督署調査の中で有休についての指摘が多くなっているため、この記事ではパート等に対する年次有給休暇について解説をします。
比例付与
パート・アルバイトに対しても当然に年次有給休暇を与えなければなりませんが、その付与日数は所定労働日数に応じて少なくできます。
所定労働日数ごとに有休日数を変える仕組みを「比例付与」といいます。通常の労働者と比べた場合の付与日数については以下のとおりです。
【年次有給休暇比例付与一覧表※】
※比例付与の対象となるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の場合
|
週所定日数 |
勤続年数(年) |
|||||||
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5 |
|
|
|
通常 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
|
|
4日 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
|
|
3日 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
2日 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
|
1日 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合、以下のとおり年間の所定労働日数をもとに区分する。
|
169日~216日 |
121日~168日 |
73日~120日 |
48日~72日 |
|
週4日扱い |
週3日扱い |
週2日扱い |
週1日扱い |
有給休暇を取得した日の賃金計算
月給の労働者の場合、年次有給休暇を取得した時には「月次の固定給を減額しない」という計算で済みますが、
時間給や日給で支給をすることの多いパート・アルバイトについてはその計算に迷うことがあります。
時給制のパート・アルバイトが有給休暇を取得した日の賃金計算の選択肢としては以下の3種類があります。
【1. 休暇を取得した日の所定労働時間×時給】
まずはこの計算方法が一般的でしょう。労働条件通知書やシフトなどで決まっているその労働者のその日の所定労働時間分の賃金計算をします。
【2. 社会保険の標準報酬日額】
労使協定を締結することにより、有給休暇1日分の計算に社会保険の標準報酬日額を用いることができます。標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割った額を指します。
【3. 平均賃金】
上記1、2以外に、労働基準法上の平均賃金を用いることもできます。平均賃金の計算式は次の①②の高い方を採用します。
① 有休取得をした賃金計算期間の前3ヶ月の総賃金÷同3ヶ月の総暦日数
② 有休取得をした賃金計算期間の前3ヶ月の総賃金÷同3ヶ月の総労働日数×60%
この平均賃金は他の計算に比べて金額が小さくなることが多いですが、有給休暇の賃金を抑える目的でパート等だけ平均賃金計算を用いることは公平性の観点から問題となる可能性があります。
労務問題対策には専門家の支援を
当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】